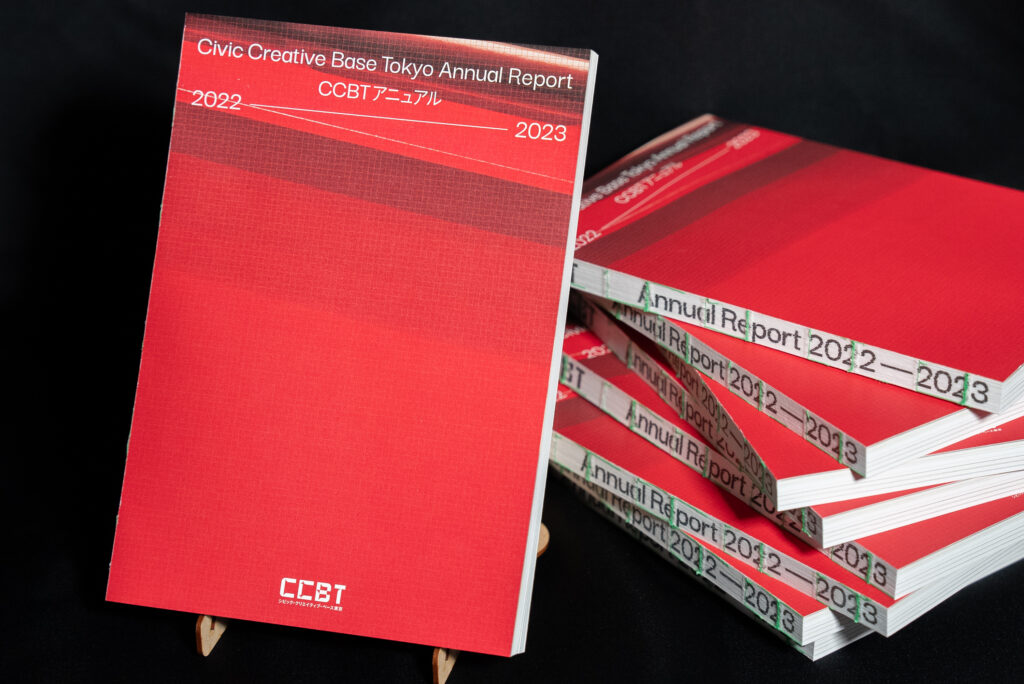2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動をまとめた『CCBTアニュアル 2022–2023』を刊行しました。PDF版は、本ウェブサイト上で公開しています。本記事ではその一部、2022年度 アーティスト・フェローであるSIDE COREへのインタビューを紹介します。
ストリートカルチャーが問う、個人と公共をつなぐ新しいコミュニケーションのかたち
SIDE COREは、公共空間や路上を舞台に、ストリートカルチャーを切り口として都市のあり方に新たな視点をもたらすことを試みるアートコレクティブ。データ化・可視化されている都市環境に対して、その多くがいまだ謎に包まれている「都市の地下空間」をテーマに新作「rode work ver. under city」をCCBTのアート・インキュベーション・プログラムにて制作しました。本作は、CCBTでの発表以降も都市の変化する姿をとらえるため、発表場所に応じたかたちで進化を続けています。ここでは、SIDE COREメンバーの高須咲恵、松下徹、映像ディレクターとして参加する播本和宜に、CCBTとの共創のプロセス、そしてストリートカルチャーと行政の境界を超える試みについて話を伺いました。

テクノロジーを通じて見えてくる都市のあり方
(播本)僕は元々メディアアートについて学んでいたのもあり、CCBTというテクノロジーにまつわる表現をテーマにした新しい施設ができることを友人から聞いて、すぐに興味を持ちました。最初はまだ全体像が見えていなかったものの、関わっていくうちにここが実験的な表現に挑戦できる場所だと感じるようになりました。
(松下)正直に言えば、最初はSIDE COREとしてメディアアートのフィールドで何ができるのか、具体的には見えていませんでした。メディアアートというとどうしても特別にテクノロジーを扱うアートとして見られがちですが、実際にはテクノロジーが意味する領域は広く、メディアアートがカバーする範囲も変化していると思います。一方で、播本はCCBTのプログラムで新しい仕事ができることを早い段階でビジョンとして持っていました。僕たちはそのビジョンを当時完全には理解していませんでしたが、今回の作品に取り組むうちに遠い存在だと思っていたメディアアートが、実はもっと身近にアクセスできるものになりつつあるのではないか、と感じ始めたんです。
(播本)アート・インキュベーション・プログラムへの応募は、2022年度の募集テーマ「東京のユースカルチャーを表現する映像作品」が、僕たちのこれまでの制作とリンクする部分があったということが大きな理由です。例えば、街なかや工事現場を模したスケートパークでスケーターたちが疾走する映像作品など、これまで都市を舞台にした映像作品をいくつもつくっていました。フェロー活動を通じてほかのアーティストや技術者とも関わることで、新しい表現が生まれるかもしれないという期待感もありました。
(高須)「rode work ver. under city」では、テクノロジーが都市にもたらしている循環を考えることに大きな可能性を感じました。それをどれだけ体現できたかは分かりませんが、テクノロジーを使いこなす能力を持つ人たちと協働することで、新しい表現が生まれる可能性は大いにあると思います。空間の3Dスキャンやプログラミングなど、SIDE COREメンバーでは持ち得えないメディアを操る人たちとの共同作業は、とても刺激的でした。
(松下)僕たちが都市を見つめるとき、例えばGoogle マップのようなデジタルツールを通じてその空間をとらえています。都市がネットワーク化されているからこそ、それに基づく考え方や物の見方があるわけです。SNSなどのデジタルプラットフォームにおいても同様です。テクノロジーを介して都市を見る視点を取り入れることで、普段身体的に都市を感じるだけでは気づかなかった新しい姿が立ち現れてきました。テクノロジーを介して都市を捉え直すこと、それが今回の作品のテーマの一つになりました。

都市の地下空間を可視化するプロジェクト「rode work ver. under city」が生まれるまで
(高須)本作に取り組むきっかけに、これまで制作してきた作品シリーズ「rode work」があります。2017年に初めて発表した作品では、復興工事の渦中にある宮城県石巻市の南浜区が舞台になっています。変化し続ける都市環境をスケートボードを通じて映し出す、映像インスタレーションを制作しました。その後、スケートボードで工事中の街を滑る様子を、再開発が進み続ける東京で撮影した「rode work ver. tokyo」へと発展し、その最新作を制作するためにCCBTのフェローに挑みました。ところが渋谷での撮影を計画する中で、路上でのスケートボードは実質的に禁止されており、撮影許可の取得が困難ということが分かりました。路上での撮影が難しいと判明したため、この制約を逆手に取って普段立ち入ることが難しい地下空間にアクセスして撮影するというアイデアにたどり着きました。
(松下)CCBTには、撮影準備のために頻繁に足を運びました。最大の挑戦は、撮影した全9カ所の場所から撮影許可をもらうことでしたが、CCBTの担当スタッフが、制作の段階から各機関との交渉を丁寧にサポートしてくれたことにより、撮影が実現しました。アーティストだけでこの準備を進めるのはかなり難しかったと思います。CCBTのスタッフには当日の撮影にも同行してもらい、まさにともにつくっているという感覚がありました。これまでもほかのプログラムでサポートを受けた経験はありますが、ここまで一緒に取り組んでくれるケースは初めてでした。
(高須)作品の発表は、東京の地盤沈下と地下水位の状況を観測する「目黒観測井」という、地下と繋がりを持つ場所で行いました。大型モニターを使った野外展示です。撮影を進めながら「どのように見せるか」を決めていったので、当初の計画通りに進んだわけではなく、かなり実験的なプロセスになりました。
(松下)成果展示の時点で一旦作品は完成しましたが、この作品を別の場所で展示する場合は、空間や状況に合わせて作品自体を調整することが必要です。というのも、都市は常に変化し続けており、特に「rode work」シリーズではその変化を捉えることが重要です。震災復興はまだ終わっておらず、都市の姿も刻々と変わっていく。そのため、発表の度に新たに撮影を行ったり、編集を加えたりと、作品を更新し続けていくことが本シリーズの特性の一つとなっています。

地下空間の発見と作品への影響
(松下)今回のプロジェクトで特に印象的だったのは、地下という空間に対する新たな発見があったことです。地下に潜ってリサーチを進めるうちに、地表からは見えない、データ化されていない空間が広がっていることに気づきました。例えば、水はけが悪い土地の地下には建物の面積に合わせて貯水タンクがあり、さらに地下鉄や高速道路、下水管等が複雑に張り巡らされていることが分かりました。つまり、地上の東京と同じくらいの面積を持つ「逆さまの東京」が地下に広がっている可能性がある。もしかすると、地下の空間は地上よりも広大かもしれません。また、地下の真っ暗な空間に入ると、怖いと感じるどころか、むしろ落ち着きを感じます。普段より音がはっきりと聞こえてきて、自分の頭の中に入り込んでいるような感覚になり、瞑想に近い状態になるんです。地下空間が神秘主義やSFにもたらしてきた影響を、身をもって体験した感じでした。
(高須)環状七号線地下調節池にあるトンネルでの撮影も印象に残っています。暗闇の中で空間の3Dスキャンを行ったのですが、通信が繋がらない中での撮影はとても大変で、撮影中のコミュニケーション方法を模索しながら進めました。建造物ほどのサイズ感を持つ巨大な地下空間に足を踏み入れることは新鮮な体験でもあって、自分の位置感覚や時間感覚が曖昧になる瞬間があったのを覚えています。

ストリートカルチャーと行政、二つの境界を超える試み
(松下)ストリートカルチャーの視点では、行政はどうしても対立的な存在として見えがちです。交渉を進めていく中で、お互いに駆け引きをしなければならない場面もありますし、共闘することは難しいと感じることも少なくありません。これは、政治と個人の関係にも当てはまる話で、集団と個人では理念が異なる部分もあると思います。しかし、それでも異なる立場を利用し合うことで信頼関係を築くことはできる。たとえ敵対的な関係が完全に解消されなくても、対話を通じて共通の理解を深め、コミュニケーションを取ることが重要です。例えば今回、スケートボードの撮影に関しては、許可が下りるとは想像もしていませんでした。しかしCCBTと協働することで、現実的には不可能だと思っていたことが実現したわけです。その結果、良い作品をつくることができ、行政側も自分たちが管理する場所の新しい活用方法を見出すことができたと思います。
※本プロジェクトは2022年度CCBTアーティスト・フェロー プログラムの一環で実施されました

『CCBTアニュアル 2022–2023』
シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]の2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動を体系的にまとめたアニュアル本。CCBTを拠点に展開された32のプロジェクトやイベントを紹介するとともに、参画したアーティストや参加者の方々のインタビューを掲載しています。
※書籍はCCBTほか、全国の美術館のライブラリーや美術大学の図書館等でもご覧いただけます。
詳細はこちら