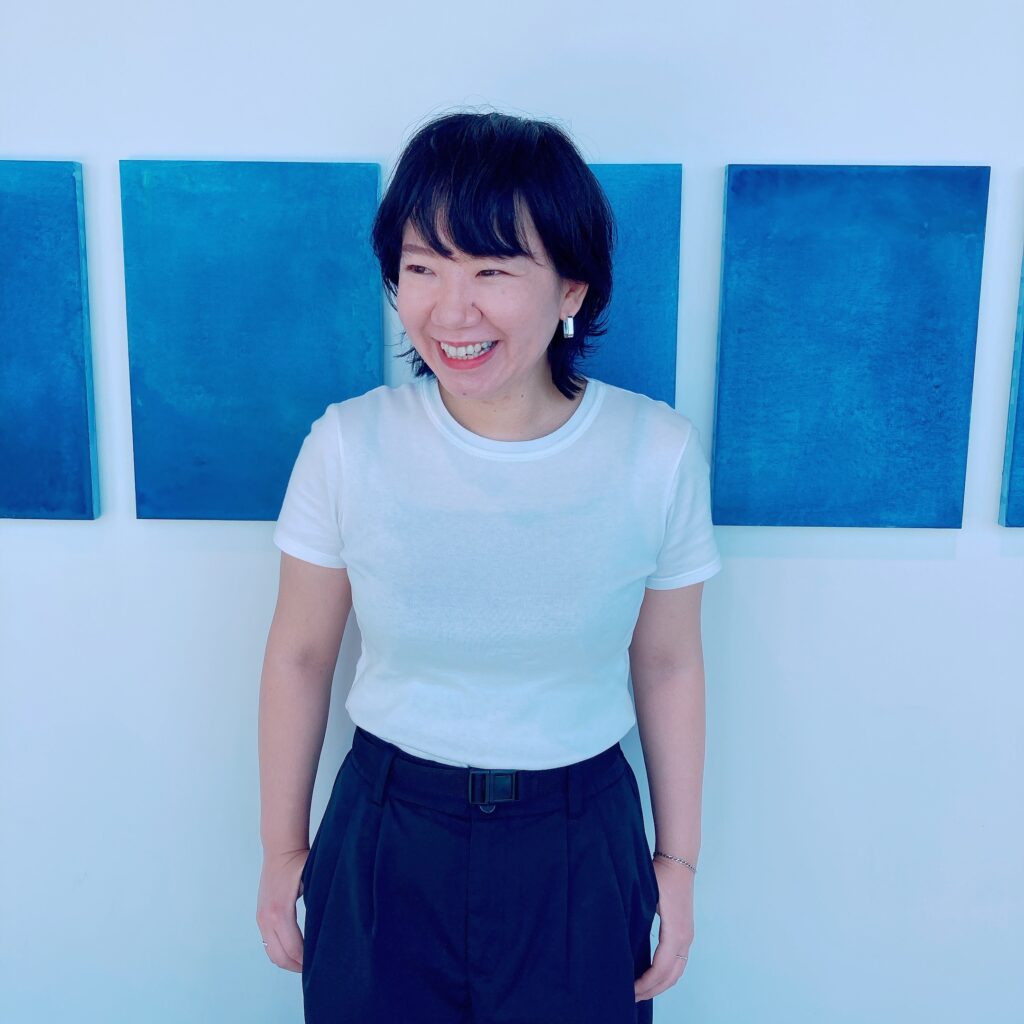「Future Ideations Camp Vol.6:見えないルールの中で都市を取り戻す」にてディレクターを務める建築家の津川恵理と、メインビジュアルを制作したおおつきしゅうとの二人が対談。津川氏は、渋谷のメインストリートである渋谷公園通り周辺エリアのリデザインを提案する「渋谷公園通り2040デザインコンペ」にて最優秀賞を受賞し、文化とその質感を都市に浸透させるコンセプトを描いています。おおつき氏は、都市における消費行為と創造行為の関係を問い直す「ポストシティーボーイ」を提唱し、グラフィックデザインを成立させる構造=都市について考えながら、渋谷やその他の都心の商業施設のイベント広告や文化施設のサインやマークデザイン等に携わっています。対談では、二人が渋谷という都市とどのように関わってきたのか、そして、建築とグラフィックデザインは都市をどのように変えうるのか、計画と計画外、大きなスケールと小さなコミュニティといった視点から議論します。
市民として:失われた渋谷のカルチャー
津川:私が渋谷と最初に関わったのは、学生の頃でした。「突撃洋服店」1というお店が公園通りの裏にあって通っていたんですよ。神戸と渋谷の2店舗で、世界中から集めてきた一点もののヴィンテージが揃ってました。でも、コロナ中に実店舗がなくなってしまって。それには寂しさや渋谷に対する違和感のようなものを感じていたと思います。それから「渋谷公園通り 2040 デザインコンペ」がたまたまはじまって、あらためて渋谷に対して思っていたことをリサーチしながらまとめていくことになりました。歴史を調べていくと例えば「突撃洋服店」は、80年代に公園通り沿いにあったのですが、表通りから裏通りへと移転し、そして別の場所へ移っていった。そういうカルチャー、都市、私の実体験を結ぶ線が見えてきた経緯がありました。
おおつき:僕は東京生まれで、渋谷は小さい頃から馴染みがないわけではありませんでした。かなり前ですが、エッシャーを見にBunkamuraの美術館へ行った思い出があります。うっすらとですけど、すっごい長い靴下を履いた女子高生たちが歩いていた記憶がありますね。
津川:ルーズソックスだ! ギャル文化の時代ですね。
おおつき:そうです。ちょっと怖い場所だなと思っていたし、中学生までは自分の意思で行ったことはなくて、バンドを組んでライブをするようになったりしてからまた行くようになりました。定期的に2010年代以降の渋谷を観察し続けてきた感覚です。あらためて考えてみるとそれは、渋谷らしい文化がなくなってからの時代じゃないかと思うんです。裏原文化やストリートカルチャーの残り香は、ハンズ向かいの「ゴールドラッシュ」付近には点々とあったけど、いざ自分が購買層の年齢になったときにはほとんどなくなっていて。あったとしてもそれは過去のリバイバルとしてあるということに気が付いたんです。「渋谷スクランブルスクエア」という建物の名称にもあらわれているように、渋谷が渋谷自体を再現するようになった。そういうことが起きている街、という印象です。

クリエイターとして:都市へ参加する態度、スケール感
津川:建築家として渋谷に関わる態度としては、目に見えない他者を想像することが重要だと思っています。私の建築家としての最初の仕事は、広場の設計(神戸三宮駅前広場)でした。扉も窓もない場を与えられて、そこに不特定多数の人々が来るという枠組みのない公共空間からスタートしています。建築は、屋根ひとつだけある東屋から個人住宅、駅などの公共空間まで幅広い種類が存在している。建築史に名を残すのであれば公共建築は建築家が憧れるもので、キャリアのなかでは50歳代で取り掛かるようなイメージです。ただ、たぶん私は建築と同時に社会のほうにも興味があって、都市に対してどのように線を引くかということに最初からこだわりがあるんだと思います。だからこそ、クリエイターが想像する他者が自己を超えた他者になっているかどうか、ある世界観に閉じていないかどうかに意識的であろうとしていますね。
おおつき:広告なんかもそうだと思うのですが、そもそも大きなスケールで仕事をしたいと思うのはなぜなんでしょう。さきほど建築家は公共建築に憧れるという話もありましたが、大きなインパクトとともに大衆と関わることをすごく大事にしていると思いました。なぜと質問をしたのは、デザインや建築を通して何かを大きく変えるということはポジティブに捉えられる一方で、すごく危険なことでもあると思ったからなんですよね。そのうえで、より多くの人へ向けたものをつくることの魅力はなんだと思いますか?
津川:すごい質問ですね(笑)、そうだなあ……。生きることって本来は非合理的な出来事の連続だけど、サービスや物が溢れてそれに慣れてしまったいま、非合理的なアクションに対して人がまったく親近感を覚えなくなっている。だからそういう社会に対して、そろそろ動かないといけないタイミングが来てない?と思うし、そう思っているならアクションしないわけにはいかない。そんな気持ちなので、ただ社会に波及力があることやりたいというよりは、私はこう思ってるんだけどどう思う?と、より多くの人に投げかけてみたい。もちろん受け手はそんなスタンスではないのも分かっているので、うまく投げかけて気が付く人は気が付くような絶妙な状況をつくりたいのかもしれません。そして、生きているあいだに私は次の時代を見たいんですよね。
おおつき:面白いですね! 僕も津川さんとかなり近い意見です。大勢の人が目を向けている場所で問いたいことがたくさんあります。グラフィックデザインの観点からすると、印刷の仕様ひとつとっても、例えば工場に発注する仕方を少し変えた印刷物を制作することでいままでスムーズに機能していた大量印刷の工程や仕組みを見直すことにも繋がります。出来上がった印刷物が掲出された街の風景から、新たな発見や都心的な退屈を抜け出すきっかけが生まれると考えています。そういった現実のなかにある決められたルールの内側を見つめ対峙することで、ルールの外側や予定調和の向こう側を意識するきっかけやアイデアを思いつく、相互作用的な創造性に富んだコミュニケーションが生まれることを期待しています。

放っておかれて育つ、ルール外の文化とコミュニティ
おおつき:CCBT含め、街には小さなコミュニティがたくさんあります。ある意味、閉じているなかでこそ交わされる議論や意識の変化もあると思うんですね。そういった小さなコミュニティの機能や創造性についてはどう思いますか?
津川:小さなコミュニティは、いまある社会像から一歩離れた少人数の小社会で、実験的に他人との関係を想像する場になる。だからすごく重要だと思います。「渋谷公園通り 2040 デザインコンペ」のプレゼンでは、パース図のほかに組織図も提出したんです。設計的には「テアトロン」2という場を用意しているだけなので、まちづくり協議会という組織も設計して、自由と自治の双方が成立するための座組みを提案しました。そこにはキュレーターのポジションが組み込まれていて、表現から商業まで組織として判断できる体制になっています。ここから小さなコミュニティが生まれていく想定で、ひとつのテアトロンだけを使う場合もあるし、すべてを使った大きな祭典の場合もある。そういうコミュニティのスケールがいろいろと都市にあると面白いんじゃないかということを提案したんですね。
おおつき:なるほど、それでいうと少し関係ない話から始まるのですが、渋谷や原宿のストリートカルチャーは国外でも人気で、それ自体が観光の対象になっているようにも感じます。そもそも渋谷に限らず、ユースカルチャーは用意された土地で計画されてつくられるというより、自発的に生まれ、整備されないからこそ起こりうる文化の一例だと思います。建築家の仕事では計画が必要ですが、そういった計画外のことは必ず起きますよね? その計画外を楽しみたいと思って都心を目指してくる人々も多いと感じています。相互作用から広がっていくコミュニケーションが増えるなかで計画外を楽しむクリエイティブな消費者に向けた発信は増えていくんじゃないでしょうか。彼らが二次創作的に創造しながら小さなコミュニティを盛り上げていくことが、自発的な街の活気に繋がっていくことに関してはどう思いますか?
津川:放っておかれて育つというのは、まさに私が建築でやろうとしていることで。建築計画を超えて、活き活きとした人の振舞いが連鎖的に生まれていく状況を建築で目指しています。もともと私は身体表現者になりたかったんです。10代の頃はまさに放っておかれても毎日腹筋100回するくらい没頭していた(笑)。例えばダンスは、身体のプロポーションの連続で成り立っていて、上手な人はどこで動画を止めても美しいんです。そこに偽りのないピュアな感性が言語を超えて表現されていると感じ、それが私は好きだったんですよ。その身体表現への熱量を建築で超えなければ建築にも没頭できないと思い、何とか身体表現と建築を結びつけていった結果、「いかに建築がもつルールから外れた状況を生み、そこで身体が活き活きと過ごしていくか」という方向にシフトしていきました。身体表現(日常における人のちょっとした振舞い)は、まさに建築の中で起こり、建築計画の外にあるものだからです。じゃあどうやってクリエイティブなユーザーを建築で成立させるか。青木淳さんが論考で書かれていたのは「ルールのオーバードライブ」3という言葉で、ルールの設定が秀逸であれば、オーバードライブ(つくり手の意図からの自律)が起こり、クリエイティブな発想がたくさん生まれてくる。そんなふうに私のなかでロジックが通っています。サッカーも幼少期から大好きでよく観るのですが、手を使わずにただ足だけを使うというシンプルで普遍的なルールだったからこそ、それをどう乗り超えていくか、プレーヤーが自然と考えるようになる。サッカー選手たちのネットワーク的な動きには建築的なもの、アーキテクチャがあって、セットプレーの流れを目で追っていると美しい幾何学が出てきます。同じルールでも何万種類のプレーが存在するその有り様に、「これぞ人が生きる理由や!」って思ったり(笑)。もちろん渋谷公園通りもなんとかしないといけない部分がまだまだたくさんありますが、「設計で握るルールと手放す自由の境界を、どう設定できるか」を意識していきたいんです。
おおつき:自律的な発想や遊びが起こることを想定して設定されたルールを、街に訪れる人がさらにそれぞれに創造的に超えていくこと。これはまさに当たり障りのない方法で消費され尽くした後の街でポストシティボーイが心がけたいことです。ルールの外側を探すためにも、まずは都市をとりまくルールそのものを意識して捉えることからはじめたいですね。

- 1985年オープン。古着でモードを表現するセレクトを行う。2020年神戸店、2021年渋谷店をクローズし、現在はポップアップ店舗のみで展開。 ↩︎
- 「シアター(劇場、舞台表現)」の意を持つ空間は道路を蛇行させることによって生じるスペースに配置され、大・中・小のテアトロンがあり、通行人の憩いの場、表現活動の場として利用される。 ↩︎
- 「決定ルール、あるいはそのオーバードライブ」青木淳(https://shinkenchiku.online/column/4579/) ↩︎

Future Ideations Camp Vol.6:見えないルールの中で都市を取り戻す
制度や規範が「見えないルール」となって編み込まれている都市に、個人がどのように介入できるのか?そこから生まれる新しい関係性とは?コモンズとしての都市を、関与と創造によって、再びわたしたちの手に取り戻すための3日間の短期集中ワークショッププログラム。
開催日時:2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)〈3日間〉
会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]
プログラムディレクター:津川恵理(建築家、ALTEMY代表)
講師・ファシリテーター:川島優志(Niantic Spatial, Inc. 副社長)、南後由和(社会学者、法政大学デザイン工学部教授)、おおつきしゅうと(ポストシティボーイ)、木原共(メディアアーティスト、ゲーム開発者)、小西隆仁(アーキテクト/ALTEMY株式会社)、杉田真理子(都市デザイナー)、谷頭和希(都市ジャーナリスト、チェーンストア研究家)、戸村陽(デジタルデザイナー /ALTEMY株式会社)、水野祐(法律家/シティライツ法律事務所)、宮内康乃(作曲家、つむぎね主宰、富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ芸術監督)、酒井瑛作 (ライター、エディター)