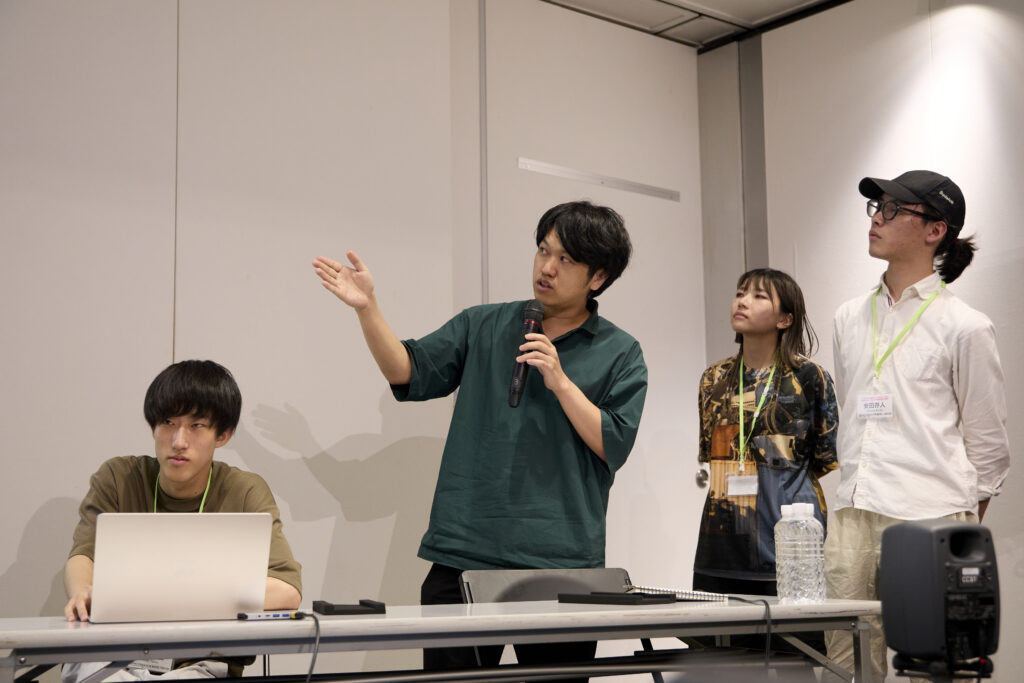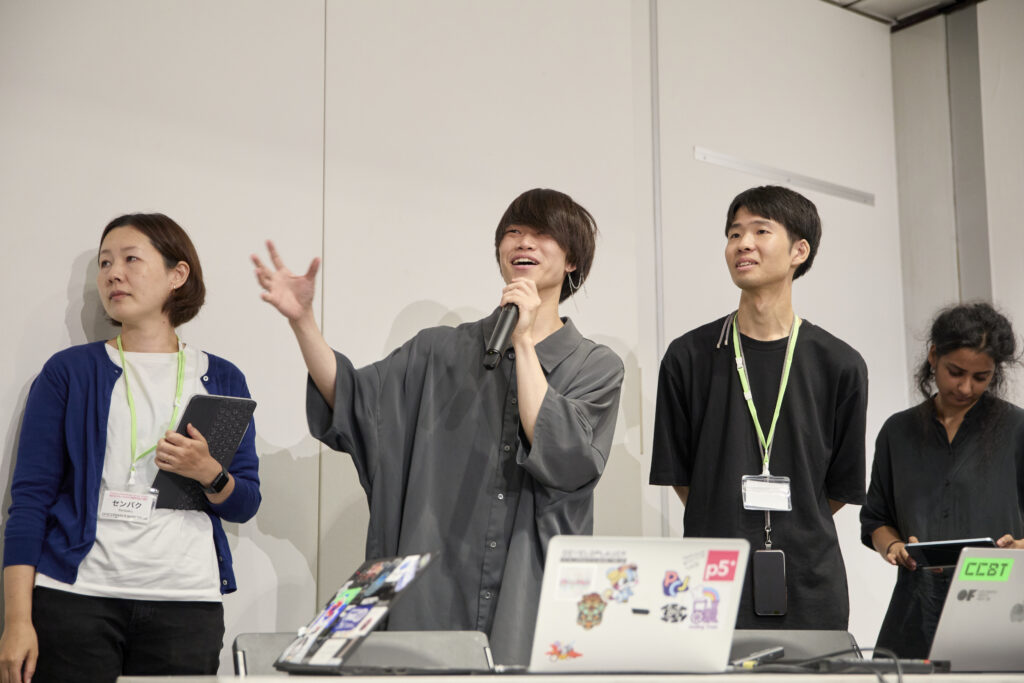公共空間と私のあいだ
DAY 1
2025.8.9
- 事業説明「本プログラムについて」
- 参加者活動紹介
- 【レクチャー】 「恣意と公共の間にある身体」
講師:津川恵理(建築家、ALTEMY代表) - 【レクチャー】 「都市へ介入するアーバン・リテラシー」
講師:南後由和(社会学者、法政大学デザイン工学部教授) - 【レクチャー】 「世界は見えているままとは限らない」
講師:川島優志(Niantic Spatial, Inc. 副社長) - 【シンポジウム】「見えない都市をさわる方法」
登壇:津川恵理(建築家、ALTEMY代表)、南後由和(社会学者、法政大学デザイン工学部教授)、水野祐(法律家/シティライツ法律事務所)、谷頭和希(都市ジャーナリスト、チェーンストア研究家)、川島優志(Niantic Spatial, Inc. 副社長)
第6回は、CCBTの年間テーマとして掲げられた「これからのコモンズ」から、都市と個人の関係性にフォーカスし、3日間の集中キャンプを通じて市民が「都市を取り戻す」ための実験を模索する。今回は、過去最大の応募者数となり、選考を経て、学生から社会人まで様々な背景を持つ24名の参加者が集った。
はじめにディレクターを務める建築家・津川恵理よりキャンプの概要説明がなされた。今回、フィールドワークおよびアイデアの対象として指定されたのは、CCBTが面する「渋谷公園通り」。「コモンズ」「都市」といった対象が広く、意味があいまいになりやすいテーマを具体化するためだ。また、都市という公共空間とアーティストやつくり手が持つ主体性や恣意性のあいだには繊細な力関係があることを意識し、「都市を題材としてアート作品を制作する」のではなく、「他者とどのように関わることができるのか」にまずは関心を向けてみるよう呼びかけられた。次に、参加者による自己紹介として制作物や研究内容などをまとめたスライドとともに約1分間のプレゼンテーションが行われ、午前のカリキュラムは終了。午後からは3名の講師によるレクチャーが開講した。
一人目の講師は、ディレクターの津川恵理。ニューヨークのデザインスタジオ「Diller Scofidio + Renfro」への参加から、ALTEMY立ち上げ、そして現在に至るまで、小さな個人の欲望からはじまったという津川の取り組みが公共的な事業へとつながっていく履歴を辿った。メガスケールの都市においていかに個人スケールの振る舞いや文化があらわれるのか。その探求の一環として神戸・三宮の駅前広場の設計、そして「渋谷公園通り2040デザインコンペ」のデザイン案などの事例が紹介された。テンポラリー(一時的)な取り組みが徐々にスケールを広げ、公共空間内の人間の振る舞いの多様さがあらわれてきた点に注目してほしいという。
二人目の講師は、著書『ひとり空間の都市論』など都市と建築に注目し、研究に取り組む社会学者の南後由和。アンリ・ルフェーヴルなど都市社会の研究を挙げ、無色透明に思える「空間」を批判的に捉えてきた社会学の成り立ちを説明。実践的な事例として、都市空間を舞台に芸術運動を行ったアンテルナシオナル・シチュアシオニストなどが紹介された。後半は、60年代から現在までの渋谷の変遷を辿り、特にスクランブル交差点はソーシャルメディアの登場によって局所的な(再)舞台化がなされ、オンライン空間の背景として「バーチャル素材化」しつつある都市景観の事例として挙げられた。
最後の講師は、『Ingress』『Pokémon GO』などを手がけるナイアンティック社の川島優志。AR技術を活用したゲームによっていかなる現実拡張が生まれたか、ユーザーたちの取り組みとともに説明された。デジタルテクノロジーというフィルターを介して「新しい目で世界を見る」ことで、現実で見過ごされ、忘れられてきたものの再発見につながるのだという。さらに、2025年に立ち上げられた「Niantic Spatial Inc.」は、空間コンピューティングの活用を推し進め、大規模な地理空間モデルを構築し、人間と機械双方の世界への理解を深めるというミッションが示された。
DAY1の締めくくりとして、シンポジウムを開催。レクチャー講師の3名に加え、弁護士の水野祐、都市ジャーナリストの谷頭和希を迎えてそれぞれの取り組みを紹介するプレゼンテーションとディスカッションが行われた。宮下公園からMIYASHITA PARKへの変化、グラフィティライターの身体性、日本では広場ではなく道路に公共性が生まれていた点など、多岐に渡るトピックが飛び交い、活発な議論となった。初日は、インプットを中心に「都市」や「コモンズ」への理解を深め、個人として公共空間へどのように関わりを持つべきかを考える貴重な機会となった。
グループワーク・講評
DAY 2
2025.8.10
- チーム発表
- ワールドカフェ
- グループワーク
ファシリテーター:津川恵理、川島優志、おおつきしゅうと、木原共、小西隆仁、杉田真理子、戸村陽、宮内康乃、酒井瑛作、稲田駿平(CCBT) - プラン講評
DAY2は、朝からあいにくの雨のなかスタート。カリキュラムは実践パートへと移り、参加者は計6グループに分かれたのち、ファシリテーターとともにグループワークに取り組む。
まずは参加者全員がそれぞれ対話できるよう「ワールドカフェ」を実施。グループワークのメンバーを時間制で入れ替えながら、キャンプのテーマについて話し合う。テーブルの中央には、付箋と模造紙が設置され、参加者は気づきや発見を書き込んでいった。付箋には今日の天気を反映した「雨」という単語やDAY1のレクチャーで度々登場した「公園」「広場」といった単語が見られた。この場ではじめて知り合った参加者同士の対話は途切れることなく、和やかな雰囲気で交流を深めることができた。
お昼休憩を挟み午後からは午前中に発表されたグループに戻り、いよいよ成果展示に向けたグループワークが開始された。各グループはここからアイデアを出し、用いる表現手段(メディアなど)を定め、大まかなプランの方向性を固めていくことになる。開始後、早速フィールドワークへと繰り出したグループは、建築物と道路を隔てる「境界線」に着目。PARCOを取り囲む線に沿ってスキャン撮影を行った。その後、他グループも続々と外出し、「傘」「味わい」「定点カメラ」などそれぞれの観点から公園通り沿いを観察していた。
夕方からは各グループによる中間報告を実施。ディレクター津川恵理、川島優志をはじめとしたファシリテーター陣の講評が行われた。発表されたのは、「捨てられたビニール傘のリサーチ」「街に流れる音楽の境界線を編み直す」「ホワイトボードを街の余白として設置する」「弁当を食べられる場所を街なかに作る」「漂着物が祀られた本殿を参拝する体験を作る」「都市を味わうレシピ」といったアイデア。講評では、ユニークなアイデアをいかに展示として成立させていくか、具体化のための方法などが議論された。
グループワーク・活動報告
DAY 3
2025.8.11
- グループワーク
ファシリテーター:津川恵理、おおつきしゅうと、木原共、小西隆仁、杉田真理子、戸村陽、宮内康乃、酒井瑛作、稲田駿平(CCBT) - 活動報告
最終日となるDAY3。成果展示に向けて本格的に制作が開始された。「やるべきことがたくさんある」と各グループは、朝から買い出し、展示物制作へと急ピッチで着手。フィールドワークの経験を
もとに構想したアイデアを形にすべく、ふたたび街へと繰り出していった。
午後からは、最終成果発表を実施。各グループは、DAY2のフィードバックをもとにブラッシュアップしたプランと展示物を発表した。展示内容の概要とフィードバックの一部を抜粋する。各グループそれぞれ渋谷公園通りをまったく異なる視点から捉え、都市空間に存在する「コモンズ」へのアクセス経路を新たに浮かび上がらせた。
・グループ1:傘が触れ合うことで鳴る楽器。
錫杖に似ていて、美しいプロダクトだと感じた(津川)。実際にやりたいと思った。100人くらいが傘を持つとどうなるのか見てみたい(木原)。
・グループ2:街に流れる音楽を多数決で変更できるアプリとスピーカー。
音には輪郭がないので境界線を意識するきっかけになる。コーンをスピーカーにするアイデアがよい(津川)。
・グループ3:自由に書き込めるホワイトボードを街に設置する。
誰でも描いて消せるとわかるホワイトボードを用いるのは秀逸。歩行者のみを対象にするだけではなく、グループのメンバー自身も観察対象として分析などをするとよい(津川)。
・グループ4:屋外で弁当を食べられるようにするツールや装飾。
誰にでも伝わるポップな面白さで即興的にハックしていた。選んだスポットのポテンシャルも示したい(津川)。ロゴマークが秀逸。古風で雑多な良さを体現しており、外で食べるという行為がしやすくなっている(おおつき)。
・グループ5:街に落ちているモノ・コト・ヒト=漂着物を祀り、参拝する体験デザイン。
場所自体に異なる文脈を与えることで、人や物に異なる意味をもたらす表現(津川)。落ちているものから意図せず恩恵を受けることが都市の特徴(木原)。
・グループ6:公園通りの坂を上り下りして発生する地面と靴底の摩擦を記録。
触覚レンズのように都市と唯一触れる足裏の媒介を変換していた。検証したことで何を獲得したのかを展示で見せたい(津川)。
3日間のキャンプを通じて都市の「見えないルール」を探り、聴覚、味覚、触覚などの普段は意識されない身体感覚から空間を捉え直す展示が提案され、都市における人間の多様な振る舞いの存在を再考する機会となった。