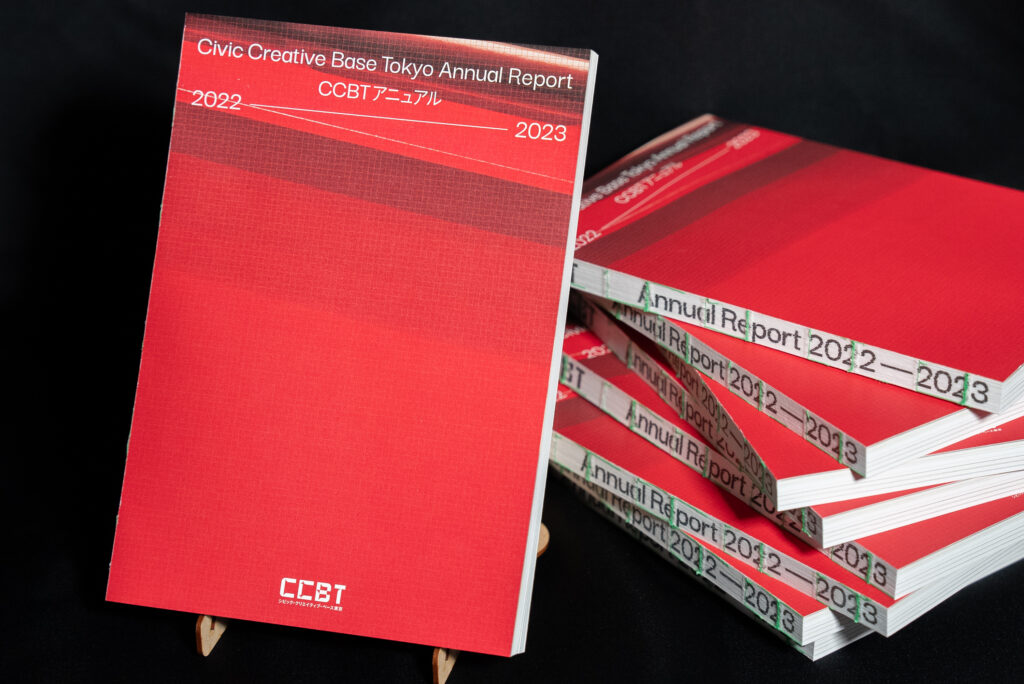2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動をまとめた『CCBTアニュアル 2022–2023』を刊行しました。PDF版は、本ウェブサイト上で公開しています。本記事ではその一部、2022年度 アーティスト・フェローであるPlayfoolへのインタビューを紹介します。
アート・インキュベーションが開放する、あそびの創造性
Playfoolは、ロンドンを拠点に活動する、ダニエル・コッペンとマルヤマ・サキによるアート・デザインユニット。「あそび」を媒介に、アートやデザイン、そしてAIといった先端技術を横断するユニークなアプローチで、ワークショップやインスタレーション、食器等のプロダクトデザイン等、様々な活動を展開しています。CCBTのアート・インキュベーション・プログラムで木原共とともに発表したプロジェクト「Deviation Game」は、CCBTでの発表以降も海外の複数都市に巡回しています。国際的にも注目されている二人に、本プロジェクトのプロセス、そしてアートとデザインの領域を横断しながら、「あそび」を追求する姿勢について話を伺いました。

プロジェクトを推進させた、CCBTのフェロー
(サキ)CCBTとの出会いは、メディアアーティストの木原共くんが「CCBTが今アーティスト・フェローを募集しているよ」と教えてくれたことがきっかけでした。木原くんとは以前に小規模なコラボレーションをして以来、AIやゲームの可能性について話し合っていて、いくつかのアイデアも実際にテストしていました。フェローへの応募はそのプロジェクトを次のステージに進めるのに良いタイミングだったので、本格的に彼と手を組むことにしました。みんなで東京に集まったとき、急いで企画書をまとめて応募しました。
(ダニエル)正直なところ、「Deviation Game」のような種類のプロジェクトを発展させる良い機会はこれまで多くありませんでした。掲げるテーマの性質上、どういった領域に位置付けてよいかが悩ましかったからです。「Deviation Game」はゲームでありながら、同時に技術的な実験でもあります。その点、CCBTの募集内容は広く開かれていて、いろんな人と一緒にAIとの付き合い方を考えるこのプロジェクトと相性が良いと感じました。
人間がAIをあざむくゲーム作品「Deviation Game」ができるまで
(サキ)最初は3人でたくさんのアイデアを持ち寄り、テストするところから始めました。そのときはビデオゲームというより、ボードゲームをイメージしてAIと遊ぼうとしていた記憶があります。数年前から木原くんはAIのモデルを研究し、ゲームとして成立させるためのAIの使い方を考えていました。そこで私たちはいくつかのアイデアをテストプレイしながら、それをどのように進化させられるかを考えていったんです。結果的に遊んで一番楽しく、AIとの向き合い方も自然に感じられた「人間がAIの目をかいくぐる」という木原くんのアイデアが「Deviation Game」の原型となりました。それまでのPlayfoolではルールのない遊びを追求していたので、ルールを持つ遊びをつくるのは初めてでした。しかし、ルールを設けることで、与えられた枠を超えていこうとする、人のクリエイティビティがより可視化されることが分かり興味深かったです。その経験は、次に取り組んだプロジェクト「How (not) to get hit by a self-driving car」※にも繋がっています。「Deviation Game」を通じて、より広い意味での「遊び」をとらえられるようになった気がします。
(ダニエル)「Deviation Game ver 1.0」は、CCBTでの成果展示で発表した後、イギリスやほかの国でも展示を行いました。国ごとにプレイヤーの反応やAIに対する人間の勝率が大きく異なっていたのも興味深かったです。例えば、東京では人間の勝率は60%程度でしたが、ロンドンでは30%程度とAIが圧倒的に強い。異なる場所で展示したことで、国ごとの文化の差や、AIの学習データがいかに英語圏に偏っているかも浮き彫りになりました。この差がとても面白いし、怖いなとも感じます。一方で、国ごとの違いがあっても、誰もが共通してこのゲームをポジティブに受け止めているとも感じました。それはこの作品の、文化の差を超えた強さを示しているとも思います。


あそびを介したテクノロジーとの批判的な向き合い方
(サキ)私たちは、テクノロジーに対して常に批判的な視点を持つようにしています。新しい技術に対しても、単純に生産性向上のためのツールとして使うのではなく、もっと探究的で懐疑的な視点を持って向き合うべきだと思っています。私たちにとってテクノロジーとは、いわゆる最新のテクノロジーのみでなく、社会的なシステムや古くからの技術、テクニックといった、人間がつくり上げてきたもの全般を指します。そして、これらテクノロジーと私たちの関係が、移り変わる社会にのなかでどのように変化し、また構築されているのかを常に問いかけるようにしています。「どうしてそのナラティブが存在するのか?」、違和感があるときには「どう関係したいのか?」といった問いに対して答えを探しながら、見えにくい部分に介入することで、新たな発見があるからです。
(ダニエル)テクノロジーを起点として社会に介入することで、私たち自身について新たに発見することがあります。それがPlayfoolの興味の中心であり、自身の活動に楽しさを感じる理由でもあります。私たちが掲げる「あそび」は、ゲームなどのフォーマットやその方法についての探求ではなく、むしろ、幼少期の子どもにとってのあそびのように、人が自分なりの世界の見方を再構築し続けるための手段なのです。一方で、テクノロジーを扱う実験的で批判的なプロジェクトを推進することは難しいと感じることもあります。特にデザインのフィールドでは、アカデミックな領域では開かれた議論が活発に行われていますが、プラクティカルな実践となると、とたんにクライアントのニーズが強く影響します。実験的なアプローチを取る余地が限られているのが現実なのです。その点、メディアアートの世界では、実験的かつ批判的なアプローチをしても、それを面白がってくれる土壌が存在しています。だからこそ、技術に正面から向き合い、確証がなくても、まず試してかたちにしてみるという挑戦ができるCCBTの環境はありがたかったです。

思考の枠を取り払うCCBTでの制作体験
(サキ)CCBTでの成果発表までの3カ月間は基本的に3人とも東京に滞在して、CCBT内のラボをプロジェクトスペースとして、ガッツリ制作を行いました。ほぼ毎日いたと思います。制作のプロセスにおいて、インスピレーションを与えてくれるような信頼できるアーティストたちと同じ場所で作業することは、私たちの制作スタイルにも大きく影響しました。具体的にどう影響を受けたかを明確に言葉にするのは難しいのですが、彼らの持っている価値観や目指しているものが、自分自身の思考を自由に解放するきっかけになったと思います。同じプロジェクトをCCBTではなく、別の組織や枠組みで取り組んでいたなら、全く違うかたちの作品になっていたかもしれません。
(ダニエル)滞在制作では、多くの人が多様な方法で私たちのプロジェクトに関わってくれて、大きな支えになりました。通常、プロジェクトが始まると想定している枠に収まろうとしてしまうことが多いのですが、CCBTではそうした枠を取り払ってくれる人がたくさんいました。とにかく壁を壊して進んでいく人たちの姿を見て、私たちはどこかで「正しいやり方」にとらわれていたのだと気づかされたんです。例えば、同じく2022年度アーティスト・フェローのSIDE COREによるプロジェクトには社会に対してしっかりと介入するための「可能性の開き方」がありました。デザインのプラクティスに限界を感じていた時期でもあったので、CCBTでの活動を通じて彼らのプロセスやアプローチに触れることで、新しい広い世界を見せてもらいました。「こんなに自由にやってもいいんだ」と思えることができたのは、とても大きな発見でした。またCCBTのスタッフには何があっても諦めさせないという雰囲気があり、関わる人全員が妥協せず、作品のクオリティを高めるために向き合ってくれました。メンターもとても率直で、展示計画の初期段階では思い描いたプランがコンセプトに合わないのではないか等正直なアドバイスをくれたのも良かったです。
CCBTの最もユニークな点は、成功の確証がないのにアーティストと一緒にリスクを取ってくれるところだと思います。アーティストには迷いがつきものですが、必要なサポートを提供し、プロジェクトを一番良いかたちで進めるために並走してくれるのは本当にすごいことです。そこには信頼関係があって、だからこそ最後までプロジェクトをやり遂げられるのだと思います。
(サキ)イギリスのものづくりの現場では、みんなが安全に感じられる環境(心理的安全性)が整備されていることが重視されます。一方でCCBTでは、思い描くことを自由に、全力で挑戦できる場と環境が整備されていて、それが大きな信頼感に繋がっています。その点がCCBTの最大の魅力だと思います。私たちの制作スタイルやプロジェクトの進め方は、CCBTでの経験を通じて大きく変わりました。まさに「インキュベートされた」感覚です。
※木原共とPlayfoolによる、AIに「歩行者」と検知されないように横断歩道を渡り切る、路上を舞台にしたゲーム作品
※本プロジェクトは2022年度CCBTアーティスト・フェロー プログラムの一環で実施されました
『CCBTアニュアル 2022–2023』
シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]の2022年10月の開所から2023年度(2024年3月)までの約1年半にわたる活動を体系的にまとめたアニュアル本。CCBTを拠点に展開された32のプロジェクトやイベントを紹介するとともに、参画したアーティストや参加者の方々のインタビューを掲載しています。
※書籍はCCBTほか、全国の美術館のライブラリーや美術大学の図書館等でもご覧いただけます。
詳細はこちら